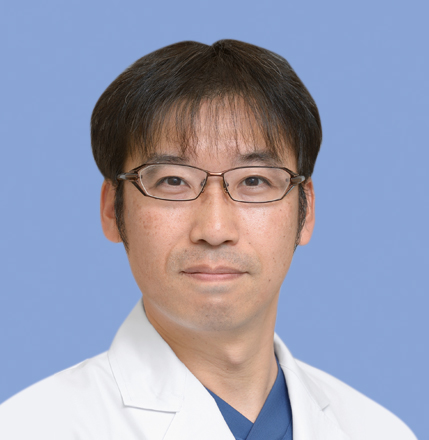栄養管理部概要
入院患者さんへ
入院した当日1食目から、安全で患者さん個人に適したお食事を提供できるように、入院前準備センターにて、食物アレルギーや食形態・食事療法の必要性などを確認し、栄養面から治療を支えています。さらに、全身麻酔での手術が予定されている患者さんには、周術期サポートチームによる栄養状態の確認も行っています。手術までに栄養状態の改善が必要な患者さんには、より早く専門的な栄養介入ができるような体制を整えており、手術後の早期回復につながるよう、多職種と連携をとっています。
入院中は、定期的に患者さん一人ひとりの状態を確認し、適切なタイミングで適切な栄養が摂れるように、食事・栄養面でのサポートを行っています。また、必要に応じて、退院後の栄養管理について患者さん・ご家族・転院先などに情報提供を行っています。各病棟に担当の管理栄養士が在籍しているので、緊急入院の場合でも、医師・看護師をはじめとした様々な職種と情報交換をして、必要な栄養が摂れる方法を検討し、早期退院を目指しています。
外来患者さんへ
生活習慣病やがん、その他の疾患などにより自宅での食事療法が必要な場合は、主治医の指示のもと、栄養相談を受けていただくことができます。
地域のみなさんへ
生活習慣病、消化器病などの教室はどなたでもご参加いただけます。
栄養管理部の活動
〈栄養相談〉
当院には様々な疾患を有する患者さんが来られますので栄養相談内容は多岐にわたります。栄養相談を行う際にはフードモデルや資料を用いてできるだけ分かりやすく説明することを心掛けています。

〈管理栄養士による食事調整〉
食思不振などでお食事が進まない患者さんには、病棟で管理栄養士がお話を伺い、お食事の調整を積極的に行っています。嚥下食などの食形態に関しても、他職種と連携しながら調整を行っています。経管栄養を行っている患者さんへの適切な投与量や投与方法についても検討しています。
スタッフ紹介
栄養管理部スタッフ
| 職名 | 氏名 |
|---|---|
| 部長代行(医師) | 岩倉 敏夫 |
| 副部長(医師) | 西岡 弘晶 |
| 副部長(医師) | 小倉 香奈子 |
| 副部長(管理栄養士) | 岩本 昌子 |
管理栄養士22名(副部長1名、主査3名、レジデント4名、パート3名含む)
専門分野における認定有資格者数(管理栄養士のみ)
| NST専門療法士 | 9名(兼務含む) |
|---|---|
| 糖尿病療養指導士 | 3名(兼務含む) |
| 病態栄養専門管理栄養士 | 6名 |
| 小児アレルギーエデュケーター | 1名(兼務含む) |
| がん病態栄養専門管理栄養士 | 2名 |
| 栄養治療専門療法士 (周術期・救急集中治療専門療法士) |
2名 |
| 心不全療養指導士 | 2名 |
| 腎臓病療養指導士 | 1名 |
| 日本摂食嚥下リハビリテーション学会認定士 | 1名 |
| 兵庫県肝炎医療コーディネーター | 1名 |
クリニカルサービス
1.栄養ケアマネージメント(NCM)
- 全入院患者さんの栄養アセスメントを行い、栄養介入の必要な方への栄養状態是正・改善に向けて、栄養補給法などのアドバイスを行っています。救急、ICUを含む全病棟に病棟担当の管理栄養士がいます。
- 入院中に、病気の影響や治療の副作用などで食欲が落ちてしまうことがありますが、その際に食べやすい料理や献立の調整をしたり、補食の提案を行っています。また、口から食べることができず、鼻や胃から管を通して栄養剤を注入したり、点滴で栄養を摂らないといけないこともありますが、こうした時にも適切な栄養剤を選択したり注入法を検討したりしています。
- 各病棟で随時栄養についてカンファレンスを行っていますが、病棟では対応が困難な場合はNST(栄養サポートチーム)に依頼をして栄養について検討を行い、適切な栄養管理を行うよう努めています。
- チーム医療の診療サポートとして各種カンファレンス・回診に参加し、栄養についてのアドバイスや情報提供を行っています。
| ①NSTカンファレンス・回診 | 1回/週 |
|---|---|
| ②NSTサテライトチームカンファレンス | 各病棟により |
| ③糖尿病カンファレンス・回診 | 1回/週 |
| ④腎臓病カンファレンス・回診 | 1回/週 |
| ⑤心臓リハビリカンファレンス | 1回/週 |
| ⑥心不全カンファレンス | 2回/月 |
| ⑦摂食嚥下カンファレンス | 1回/週 |
| ⑧嚥下ワーキング | 不定期 |
| ⑨VF(VIDEO FLUOROGRAPHY)カンファレンス | 1回/週 |
| ⑩褥瘡カンファレンス・回診 | 1回/週 |
| ⑪緩和ケアカンファレンス | 1回/週 |
| ⑫緩和ケア回診 | 3回/週 |
| ⑬E-ICU回診 | 毎日 |
| ⑭G-ICU回診 | 毎日 |
| ⑮C-HCU回診 | 1回/週 |
| ⑯SCUカンファレンス | 3回/週 |
| ⑰血液内科移植カンファレンス | 1回/週 |
| ⑱アレルギーチームカンファレンス | 不定期 |
| ⑲CIFT回診 | 1回/週 |
| ⑳総合内科カンファレンス | 1回/週 |
| ㉑膠原病・リウマチ内科カンファレンス | 1回/週 |
| ㉒地域連携カンファレンス | 各病棟により |
2.個別栄養食事相談
糖尿病、心臓病、腎臓病をはじめ、各種疾患に応じたお食事や適切な栄養の摂り方について、栄養相談を行っています。予約制となっていますので、主治医の先生にご希望の日時をお申し出ください。外来に来られた日に予約枠の空きがあれば、外来当日に栄養相談を受けていただくことも可能です。
時間:月曜日~金曜日9時から17時(火曜15時30分まで)、1回約30分です。
場所:2階栄養相談室(タリーズ斜め前にあります、りんごのマークを目印にお越しください)
入院中の患者さんで、退院後の栄養食事療法についてお話を聞きたい方は、患者さんやご家族のご都合の良い日時に病棟でお話をさせていただくこともあります。
治療を継続するための一助となるべく、外来化学療法センターでも栄養相談を行っています。食事に関するお困り事の相談や、工夫できるポイントの提案など、患者さん一人ひとりに合わせて、少しでも栄養状態を維持できるようお話ししています。
3.集団栄養食事指導
入院中の患者さんを対象に集団栄養食事指導を行っています。各種疾患のお食事や栄養療法について基本的なことについてお話しています。予約制となっています。
※いずれも退院までに、個別栄養食事相談を受けていただきます。
糖尿病集団栄養食事指導
時間:毎週火曜日 14時から 約1時間
心臓リハビリテーション
時間:毎週木曜日 14時から 約1時間
その他
- 臨地実習生の指導
- 栄養管理委員会の実施、各種委員会の対応並びに調整
- 健康教育の実施(一般市民、他部局、他施設、研修医、看護部、業務員他)
- 施設見学の調整対応
入院中のお食事について
入院中のお食事について
- 安全な食事の提供
- 適切な食事の提供
- QOLを高める食事の提供
- 行事食
- 個別オーダ対応
- 徹底した衛生管理
- 疾患に適した栄養成分別の食事の提供
- 選択メニューの導入、再加熱カートでの配膳
- 毎月行事に合わせた季節感のある食事の提供
- 治療に伴う食思不振、摂食嚥下困難、食物アレルギーなどへの対応
お食事の種類について
入院中のお食事は、一般食と特別治療食に分かれており、28日のサイクルメニューとなっています。基本的には主治医が疾患に合わせてお食事の内容を決定しますが、食形態が合っていない場合や、食事摂取量が落ちている場合には管理栄養士がお食事の内容を調整いたします。各病棟に成人食の週間献立表を掲示していますので、ご参照ください。
一般食
成人食・シニア食、また形態別では、流動食~軟菜食があります。特別な栄養の制限はありませんが、バランスよく栄養素が摂取できるようになっています。お食事があまり摂れない方にはそれぞれハーフ食があります。
一般食以外は特別治療食となります。疾患の治療に直接関与する食事で医師の指示に基づき、調整いたします。
| 《特別食非加算食》 | 小児食、産科食、潰瘍食等術後の流動食などです。 |
|---|---|
| 《特別食加算食》 | 特別治療食のうち、入院時食事療養費で加算が算定できる治療食です。主として腎臓病、肝臓病、糖尿病、胃潰瘍、膵臓病、脂質異常症に関する食事等が対象になります。 |
| 診療報酬 | 一般食 | 特別治療食 |
| 非加算 |
|
|
|---|---|---|
| 特別食加算 |
|
お食事の配膳について
当院では、調理後、チルド保存したお食事を、提供前に再加熱カート内で再加熱して提供する、ニュークックチルシステムを採用しています。お食事のトレーの半分は温配膳(主に主食、汁物、主菜など)、もう半分は冷配膳(和え物、サラダ、デザート、飲み物、パンなど)となっており、各お料理を食べるのに適した温度で患者さんのもとに配膳しています。
特別な対応について
通常のお食事が食べにくい方へ、特別な対応をしています。
一口大
魚や肉などの副食を食べやすい一口大に切り、フォークなどに刺しても食べられるようにした形態です。
一口大とろみ
一口大のお食事で、汁や流動部分にとろみをつけたお食事です。
串刺し食
検査後などで安静が必要な場合や、痛みなどがあって、寝たままの姿勢でしかお食事を摂れない場合に、食べやすくするためにお料理を全て竹串に刺したお食事です。
付加食
お食事が十分に摂れない、または摂れていても栄養量が不足している方への栄養補給のためにお食事に付加する栄養補助飲料やゼリーなどです。
禁止食
食物アレルギーに対する禁止食対応はもちろん、食欲が落ちている場合などに食べにくい食材やお料理を除いたお食事の提供を行っています。
嚥下食
脳梗塞後や神経疾患、手術後などで、食べ物や飲み物が飲み込みにくい方へのお食事です。ゼリー食、ペースト食、極刻みとろみ食など、5段階のお食事があります。
あじさい食
化学療法や放射線療法、手術後など、治療に伴って食べづらさを感じている方へのお食事です。
| 《あじさい食A》 | だしのみで調理したお食事です。すべての味を濃く感じてしまう方に向いています。 |
|---|---|
| 《あじさい食B》 | カレーライス、お好み焼き、ハンバーグ、など味の濃い料理をご用意しています。 |
| 《あじさい食C》 | 冷しゃぶの梅ポン酢、おろしうどんなど、さっぱりした料理を中心としたお食事です。食欲不振や悪心があり、酸味などのさっぱりした味付けを希望される方に向いています。 |
選択食について
| 対象食種 | 成人食、産婦食、分娩食 ※一部対象外の病棟に入院中の場合を除く |
|---|---|
| 実施曜日 | 水・木・金(祝祭日、行事食の日は除く) |
| 締切時間・場所 | ご希望の方は申し込み用紙に記入し、火曜日14時までに病棟設置の回収ボックスへ提出 |
なお、選択後の変更には対応できません。また、ご入院の日時や入院後の食種の変更などによりご希望に沿えない場合があります。ご了承ください。
行事食について
毎月、四季折々の行事に合わせたお食事の提供を行っています。
(例)
病態別教室について
糖尿病教室では、ホームページ上での情報発信を始めました 心臓病教室では、ホームページ上での情報発信を始めました 腎臓病教室では、ホームページ上での情報発信を始めました病態別教室
栄養食事療法は疾患の治療や管理に重要な役割を果たしています。治療を適切に進めていくために、以下のような教室を行っています。治療や発症予防のため、あるいは勉強のために参加される方がたくさんいらっしゃいます。いずれも予約や参加費は不要です。詳しくは各種教室のページをご参照ください。
| 対象 | 内容 | 出務者 | |
| 糖尿病教室 | 入院・外来患者さんとご家族 | 糖尿病について 食事、生活、薬、自己血糖測定 |
医師、管理栄養士、看護師、 薬剤師、臨床検査技師、理学療法士、歯科衛生士 |
| 心臓病教室 | 心臓病について 食事、薬、運動 |
医師、管理栄養士、薬剤師、理学療法士 | |
| 腎臓病教室 | 腎臓病について 食事、薬 |
医師、管理栄養士、薬剤師、理学療法士、臨床検査技師、臨床工学技士 | |
| 消化器病教室 | 消化器病について 食事、薬 |
医師、管理栄養士、薬剤師 | |
| らくらく呼吸教室 | 呼吸器リハビリテーション、呼吸器疾患と栄養 | 医師、看護師、理学療法士、 作業療法士、管理栄養士、薬剤師 |
|
| がんの教室 | がんにまつわるお話 | 医師、看護師、理学療法士、 薬剤師、管理栄養士 、医療ソーシャルワーカーなど |
臨床研究
| 研究課題名 | 説明文 (PDF) |
| ICUにおける早期栄養介入の実態について | |
|---|---|
| 入院患者の入院前の栄養スクリーニングの有効性の検討 |
レジデント制度について
レジデント制度について
当院では、管理栄養士のレジデント制度を採用しています。
その目的は、実務経験に基づいた講義と臨床実務実習を通じて、高度急性期医療に対応した臨床栄養業務、並びにチーム医療を実践できる管理栄養士を育成することです。もちろん慢性期疾患に対応する力も習得できます。
求める人材は、将来病院就職を希望しており、高度な知識と実践力、患者や医療スタッフとのコミュニケーション能力等を習得し、その後即戦力として活躍したい方や、今現在病院あるいは医療関係で働いているが、さらに幅広く専門的な知識と実践力を習得したい方などです。
教育体制
レジデント制度における研修は2年間行います。以下におおまかなプログラムを掲載していますが、個人の職務経験などに応じて若干内容は変わります。また、レジデントの研修期間中、職員の補佐として給食事務補助をお願いしています。
| 1年目(一般分野) | SOAP形式での記録、栄養指導の手順、栄養管理計画の立案方法などを習得。 | |
|---|---|---|
| 病棟栄養管理 | 各病棟(ICU・救急病棟含む)を2~3週間ごとにローテーションで回り、様々な疾患や病態への対応を学びます。その際、各病棟担当の管理栄養士が栄養介入方法などについて丁寧に指導を行います。ローテーション中の病棟の診療科のカンファレンスや回診にも参加します。 | |
| 栄養指導 |
栄養指導 個別:週1枠から2枠担当(1枠は午前もしくは午後の4時間)。 集団:糖尿病・心臓リハビリを交替で担当。 |
|
| 週1回、レジデント教育担当の管理栄養士と栄養指導や病棟での患者介入について予習を行ったり、対応に困った症例について振り返りを行う時間を設けています。毎月最終週には当月の成果や反省と翌月の目標について発表してもらいます。 | ||
| 2年目(専門分野) |
1~2病棟を担当し、急性期、重症部門やその他病態において、さらに専門性の高い栄養管理とチーム医療が実践できる実力を身につけます。担当する病棟は、今後の進路や取得したい資格などにあわせ、ある程度希望に沿えるようにしています。栄養指導も継続して担当します。 週1回のレジデント教育担当との時間は引き続きありますが、後輩レジデントの教育も行うことで、経験を積んでいきます。 |
|
先輩たちの進路
病院就職、大学院進学、大学教員など